ゆうべつ@サッポロ<新篠津村特別編4>
「新湧」開拓記<4完> 稲作への思い強く~有数の米どころへ

新湧地区の人々が待ち望んだ米作りが昭和34年(1959年)、いよいよ始まった。上湧別から入植し、泥炭地に開墾の鍬を入れた27年に畑作でスタートしてから8年目。篠津運河の掘削土を使った「送泥客土(そうでいきゃくど)」が稲作に転換する力になった。
30・50周年記念誌によると、送泥客土が行われた34~35年の2年を含め、新湧全体が水田に変わるのに3年を要した。
その3年目の36年7月、大雨が大水害をもたらし、各所で川がはんらんして農地も浸水した。これが畑作だったら収穫は「皆無に近い大悲劇」になったかもしれないが、このころには「全戸水田に移行しており、最小限の被害に終わった」という。

送泥客土が水田造りに効果的だったのは確かだ。とはいえ、これですべて完了したわけではなかった。泥炭の浮上現象や機械の大型化に対応する必要もあって、山などから土を運び、繰り返し客土が続く。泥炭地での新湧農業の歩みは、度重なる水害などの災害を乗り越えながら土地改良を続ける不断の努力の歴史だったといえる。
水田化と並行して用水路や揚水機場の整備も続き、39年の「大冷害凶作」、42年の「空前の大豊作」を経験しながら、トラクターや稲刈りのバインダーが徐々に普及。50年までに共同育苗組合の設立、大型トラクターの共同購入など農作業の効率化も進んだ。

歩調を合わせるように地域の暮らしも徐々に利便が高まっていった。
記念誌をたどると、
31年 開拓地に電灯施設が完成してランプ生活を終える
前年の暮れには試験通電があり、大みそかは明るい電気の下で楽しい年越しができた。ただ、このころはまだ生活が苦しく、「電気代を支払うのにも大変な苦労だった」という。
32年 集会所を建設。ささやかながら「焼酎と煮干し」で落成を祝う



35年 農村集合電話が開通。翌年電話交換所を地区総出で建築
このころには土壁の家が木造モルタル造りの家に建て替えられていった。ストーブの燃料も泥炭から石炭へ。
36年 簡易水道二期工事完成。40年に篠津運河の東側、42年に西側で給水が始まる
この給水開始で「井戸水に別れを告げ、それまで色が付いた御飯も本来の白い御飯に炊かれ、洗濯で茶褐色に染まった白地の洋服も真白く洗える」、電気・電話・水道がそろい「人間らしい文化生活が営めるようになりました」と喜びがつづられている。
旧上湧別町生まれで新篠津村長の石塚隆さん(71)「入植したころは手植えだったのが徐々に機械化が進み、それにともなって土地改良も進みました。40年代に入ると、中古車だったけれど、みんなで一斉に車を買い、それを並べて入魂式みたいなものをやりました。農村も豊かになって、いい時代になったと思いました」
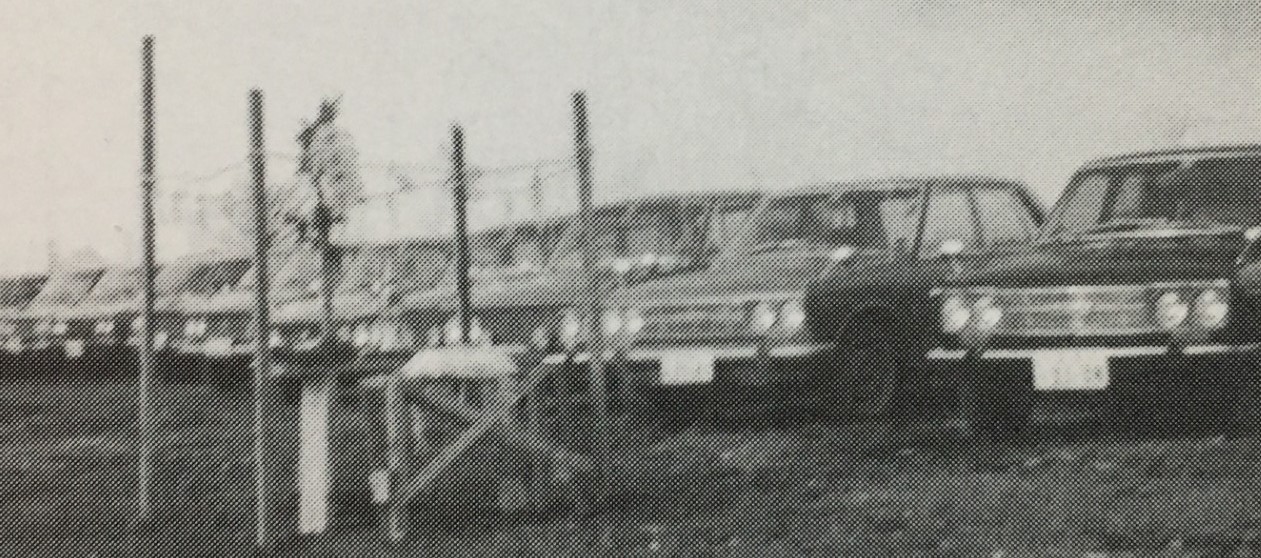
「新篠津の昭和開拓史」には「村づくりの公共施設などが逐次ととのえられ、村内の先進地区に肩をならべられるようになったのも、さほど時間を要さないほど、団結してことにあたったから」とあり、開拓民の強いきずながうかがえる。
しかし、40年代半ばに米の生産調整「減反政策」が始まり、転作にともない地域の屋台骨でもある水田は徐々に減っていく。石塚さんが高校を卒業して農業を継いだのは47年。減反が始まって間もないころだった。
石塚さん「私が農業を始めてから全部の面積で水田をやったことがありません。休んだところは豆や小麦を作るようになりました。でも、もともと泥炭地で土地改良には自己負担もあってお金をかけてきたので、どうしても米を作りたいという気持ちが強くありました」
村全体では転作した土地で大豆や小麦、野菜や花を育てつつも、米の割合は5割以上をキープしており、米作りにかける思いは強い。新篠津村の耕地面積は道内179市町村の81番目と全道の中位だが、令和5年(2023年)産水稲の作付面積は2300ヘクタール、収穫量は1万3600トンで、ともに石狩振興局管内ではトップ、全道の市町村別でもそれぞれ9位、10位とトップ10に入る、まさに「米どころ」だ。



一方で、少子高齢化、人口減といった全国共通の課題は新篠津村も同じ。新湧地区も離農者と石塚家など新規入植者との入れ替わりがあって、最初に開拓に入った30戸は50年時点で27戸に減った。30~40年代の入植者の中には旧湧別町の芭露(ばろう)や志撫子(しぶし)出身の人もいた。現在、新湧地区に残っているのは20戸ほどで、このうち農業を続けているのは、長男が後を継いだ石塚家などほぼ半数だ。
村全体でも、500~600戸あった農家は230戸ほどに。その分規模拡大が進んで、かつて1戸当たり8ヘクタール程度だった農地は22~23ヘクタールと3倍近くに増えている。
新篠津村は札幌から車で片道1時間圏内。子育て支援、教育・医療・福祉の充実など移住・定住策を進めている。また、冬にワカサギ釣りが楽しめる「しのつ湖」、温泉、キャンプ場、さらに平たんで空が見渡せる土地柄を生かした天文台や滑空場、天灯(ランタン)祭りや青空まつりなどさまざまな施設、イベントを通して交流人口、関係人口の拡大に取り組む。

石塚さん「札幌に近いことが利点であるとともに、定住が進まない側面になっている現状もあります。何といっても、新篠津村の発展を支えてきたのは基幹産業の農業です。農家がこれ以上減らないようにしたい。農業後継者として戻っている若い人たちもいます。まず農業を豊かにし、村の人たちが住んでよかったと思える地域にすることが大切だと思っています」

上湧別から入植し、かつての「不毛の地」を「豊穣の地」に変え、「米どころ」の一翼を担ってきた新湧地区。この開拓の歴史を縁に、上湧別町時代の平成15年(2003年)に両町村が友好都市提携してから20年余り経った。子どもたちの相互交流は続き、湧別が手掛ける日本酒造りに新篠津の米が使われるといった新たな動きも出ている。
最後に湧別町との交流について考えを聞いた。
「上湧別という一つの地域から20人以上の規模で同じ開拓地に入ったのは、村の中でも新湧だけでした。何かあると上湧別からきてくれたし、逆に上湧別にも行った。 母村が同じだということで一つになれて、開拓の力にもなりました。(畑作・酪農と水産業が基幹の湧別町とは)産業の形は違うけれど、この開拓があって始まった縁は、年月を経て深く重なり合い、今につながっています。若い人たちにもこの歴史を伝えながら、これからも交流を深めていきたいですね」
※新篠津村特別編はこれで終わります。連載4回の駆け足でしたが、私自身知らなかった湧別と新篠津の歴史的なつながりをほんの一端ですが垣間見ることができました。
初めて見る未開の泥炭地で苦労を重ね、米どころに育て上げた入植者、それを引き継いできた皆さんに改めて敬意を表し、今後も両町村の交流が進むことを願っています。
また、連載にあたり、話を伺った石塚隆村長をはじめ、資料を提供いただいた新篠津村や湧別町の皆さんに、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。
(取材・文/ふるさと特派員 島田賢一郎)













